中2理科の動物のふえ方についてのまとめです。「卵生」と「胎生」の比較とポイントになります。ふえ方には、卵生と胎生があります。それぞれ何類がそうなのか確かめ、正確に覚えることが大切です。それでは、中2理科の動物のふえ方「卵生」と「胎生」の比較とポイントについてのまとめをみていきましょう。
卵生と胎生
●卵生
卵を産んでなかまを増やす
- 鳥類・ハチュウ類…殻に包まれた卵で生まれる。(鳥類は、かたい殻、ハチュウ類は、やわらかい殻)
- 両生類・魚類…殻のない卵で生まれる。寒天質に包まれた卵で生まれるのが両生類
●胎生
- 哺乳類…親とよく似た子を産み、仲間を増やす。乳を飲んで育つのが哺乳類。
動物のふえ方
動物のなかまのふやし方は、大きく分けると子をうむもの(ホニュウ類)と卵をうむもの(ホニュウ類以外のセキツイ動物や無セキツイ動物がある。卵のつくりや一度にうむ卵(子)の数は動物によって異なる。
セキツイ動物のふえ方
●代表的な動物
- 魚類:サメ、イワシ、サンマ、ウナギ、フナなど
- 両生類:カエル、サンショウウオ、イモリなど
- ハチュウ類:カメ、ワニ、ヘビ、トカゲ、ヤモリなど
- 鳥類:ハト、ツバメ、ニワトリ、ペンギンなど
- ホニュウ類:ウマ、人間、ウサギ、クジラ、イルカ、コウモリなど
●魚類のふえ方
水中に非常にたくさんの卵をうむ。このため、少しぐらい卵が死んだり、ほかの動物に食べられたりしても子孫を確実に残すことができる。親にまで育つ割合(生存率)は低い。
●両生類のふえ方
両生類は、水中に比較的多く卵をうむ。 生存率は低い。 陸上で卵がかえる動物 ハチュウ類や鳥類は陸上で卵をう
む。
●ハチュウ類のふえ方
卵の数は、魚類や両生類に比べて少ない。卵は陸上の砂の中や落ち葉の下などにうむものが多く、敵に見つかりにくい。
●鳥類のふえ方
草むら、木の枝などに巣をつくり、その中に少数の卵をうむものが多い。卵の数はふつう数個であるが、魚類や両生類に比べて生存率は高い。
●ホニュウ類のふえ方
胎生で、子の数は少ないが、親が子を守るので、生存率は最も高い。
うまれる子や卵の数
魚類は産卵数が多くなっている。一方、鳥類・ホニュウ類では産卵(子)数が少なく、ほとんどのものが1~10個(ひき)となっている。
また、産卵数の多い魚類や両生類では、卵や子の多くがほかの動物に食べられてしまい、親にまで育つのはごくわずかである。しかし、もともとの卵の数が多いので、子孫は確実に残っていく。
一方、鳥類やホニュウ類の産卵(子)数は少ないが、親が卵や子の世話をするので、卵や子が生き残って、親にまで育つ割合は大きくなっている。
水中で卵がかえる動物
水中で卵がかえるセキツイ動物は、魚類・両生類である。
動物の増え方練習問題
(1)卵を産んで、なかまを増やす方法を何というか。
(2)卵を産まず、子どもを体内である程度育ててから産む方法を何というか。
●解答
(1)卵生
(2)胎生

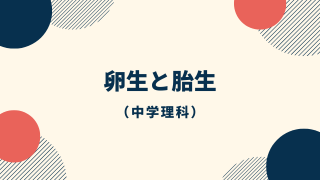
コメント