中学国語・漢字の「送り仮名」の付け方についてまとめています。送り仮名は、一つの言葉を漢字と仮名で書き表すとき、漢字の下につける仮名です。その送り仮名について掘り下げています。
送り仮名の付け方の決まり
【基本ルール】形の変わる言葉(動詞・形容詞・形容動詞)は、変わる部分から送り仮名を付ける。
(例) 帰る-帰らない 赤い-赤くなる
原則に当てはまらないもの
- 「しい」で終わる形容詞は、「し」から送り仮名を付ける。 美しい-美しくなる、楽しい-楽しけれ(ば)
- 「か」「やか」「らか」を含む形容動詞は、その部分から送り仮名を付ける。静かだ 鮮やかだ 明らかだ
- 読み間違えやすいものなどは、よぶんに送り仮名を付ける。 味わう 危ない 新ただ
名詞には送り仮名を付けない
窓、手紙、今日など。原則に当てはまらないものとして、ほかの読み方と読み間違えやすいものには、区別するために付ける。後ろ、幸せ、情けなど。
- ほかの言葉から名詞になったものは、もとの言葉の送り仮名の付け方にならう。 (例)流れ-流れる、明るさ-明るい、確かさ-確かだ
- 例外として、次のようなものには送り仮名を付けない。 話-話す、光-光る、折-折る
- これまでの習慣に従い、送り仮名を付けないものがある。 合図、受付、立場、物語
副詞・連体詞は最後の音節を送る
必ず、少し、自らなど。原則に当てはまらないものとして、直ちに、大いに、明くるなど。
複合語の送り仮名
三つ以上の言葉が一つになったもの)の場合は、もとの送り仮名の付け方による。
- 受け取る-受ける+取る
- 聞き苦しい-聞く+苦しい
原則に当てはまらないものとして、組合、小包、試合、日付など。
間違えやすい漢字の送り仮名一覧
| 読み | 正しい | 間違い |
|---|---|---|
| あぶない | 危ない | 危い |
| あらわす | 表す | 表わす |
| あわただしい | 慌ただしい | 慌だしい |
| うけたまわる | 承る | 承わる |
| おぎなう | 補う | 補なう |
| おさない | 幼い | 幼ない |
| おこなう | 行う | 行なう |
| すてる | 捨てる | 捨る |
| みじかい | 短い | 短かい |
| たしかめる | 確かめる | 確める |
| ことわる | 断る | 断わる |
| こころみる | 試みる | 試る |
以上が、中学国語・漢字の「送り仮名」の付け方となります。

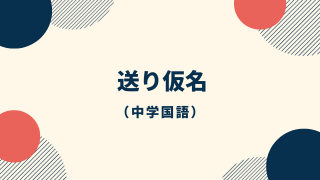
コメント