中1理科「身のまわりの物質のポイントまとめ」です。
身のまわりの物質のポイント
金属には、共通の性質があり、金属以外の物質を非金属という。有機物は炭素をふくみ、燃えて炭になったり、二酸化炭素を発生したりします。有機物以外の物質を無機物といいます。このあたりについて、詳しく解説しています。
有機物
炭素を含む物質で、燃やすと二酸化炭素が発生する物質。有機物は炭素Cという元素を含んでいるので、燃やすと二酸化炭素CO2が発生します。有機物は、木やプラスチックのように、燃えた後に炭やすすが発生するような物質も有機物になります。また、石油や石炭、天然ガス、エタノール、油、ろうのように燃料となる物質も有機物です。
有機物の燃焼
有機物を燃焼させると、次の2つの物質が発生します。
- 二酸化炭素(CO2)…石灰水が白くにごったことからわかる
- 水(H2O)…集気びんの内側が白くくもったことからわかる
また、二酸化炭素と水が発生したことから、有機物には次の2つの原子が含まれているとわかります。
- 炭素原子C…二酸化炭素(CO2)が発生したことからわかる
- 水素原子H…水(H2O)が発生したことからわかる
有機物は炭素Cと水素Hを含む化合物であることがわかります。
無機物
物質を加熱しても焦げずに二酸化炭素も出さない物質(変化しない物資)が無機物
プラスチック
プラスチックの性質は、
- 燃えて二酸化炭素を発生する
- 一般的に軽い
- 割れにくい
- さびない
- くさりにくい
- 電流を通しにくい
- 加工しやすい
金属
金属は大きく5つの性質を持っています。
- 展性…たたくと薄く広がる
- 延性…引っ張ると細く伸びる
- 金属光沢…磨くと光る(金属特有の輝き)
- 電気伝導性…電気をよく通す
- 熱伝導性…熱が伝わりやすい
※磁石にくっつくは、すべての金属にあてはまるわけでないので、金属の性質には分類されません。また、上の5つのすべての性質をもって、金属といいます。
金属の種類
金属は重い金属と軽い金属があります。
- 重い金属…鉄、銅、銀、金などです。
- 軽い金属…アルミニウムなど。
金属以外のものを非金属といいます。理科では、特に、非金属として、以下の例が挙げられます。紙、砂糖、食塩などです。
日常の中にある金属
日常の中にある金属は、ほとんどが「合金」と呼ばれるものです。合金とは、純金属の欠点を改善するために母体金属に他の金属などを溶かし合わせたものです。金物によく用いる材料である鋼は、鉄に炭素を加えた「鉄合金」ということになります。銅に亜鉛を加えた「銅合金」、その他、アルミニウム合金、亜鉛合金といったものがあります。
金属の利用
板などを造る「圧延」、コインや刀などを造る「鍛造」、ネジを造る「転造」、サッシなどをつくる「押出し」など利用があります。これは多くの金属がもつ塑性(思いのままに曲げて自由な形に変形させることができる性質)を利用した代表的な加工といえます。また、金属の弾性を利用したものとしてバネなどもあります。
身のまわりの物質の練習問題
次の問いに答えよ。
(1)金属の性質である、特有の輝きを何というか。
(2)金属の性質である、たたくとうすく広がる性質を何というか。
(3)金属の性質である、引くと細長く伸びる性質を何というか。
(4)金属の性質である、電気をよく通す性質を漢字五文字で何というか。
(5)金属の性質である、熱をよく通す性質を漢字四文字で何というか。
(6)金属の性質に「磁石につくこと」は「含まれる」と「含まれない」のどちらか。?
(7)金属でない物質を何というか。
(8)銅は、磁石にくっつか、くっつかないか。
(9)銅は、紙やすりでこすると、何色に光るか。
(10)アルミニウムは、磁石にくっつか、くっつかないか。
身のまわりの物質の解答
(1)金属光沢
(2)展性
(3)延性
(4)電気伝導性
(5)熱伝導性
(6)含まれない
(7)非金属
(8)くっつかない
(9)赤
(10)くっつかない

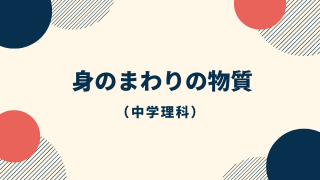
コメント