中学公民・入試に出る「自衛隊と日本の防衛の年表・年号」まとめです。昨今の入試では、時事的な問題を絡めての出題が目立ちます。中でも、国際関係、自衛隊、防衛、平和に関する問題はよく出題されます。今回は、日本の防衛の歴史について復習しておきましょう。それでは、中学公民・入試に出る「自衛隊と日本の防衛の年表・年号」まとめです。
日本の防衛
日本は、防衛のためアメリカ合衆国との間に、日米安全保障条約を結んでいます。この条約は、他国が日本の領土を攻撃したときに、日米が共同で対処することを約束したものです。そのため、駐留するアメリカ軍に必要な基地を提供しています。
政府は、安全保障政策の原則として、専守防衛を基本に、核兵器を「持たず、つくらず、持ち込ませず」の非核三原則を守り、文民統制を確立しています。自衛隊は、文民である内閣総理大臣と防衛大臣が指揮するしくみがとられています。
文民統制
文民統制(シベリアン=コントロール)とは、軍隊を市民の代表者が統制するという民主主義の原則で、自衛隊法も文民統制を定めています。先述のように。内閣総理大臣と防衛大臣が自衛隊を指揮し、国会が自衛隊の定員や組織を、法律や予算で決定するというしくみがとられています。
国連平和維持活動(PKO)協力法
1992年に、国連平和維持活動(PKO)協力法が成立します。PKOへの自衛隊の海外派遣と、その小型武器の所有が認められ、カンボジア、モザンビーク、東ティモールなどに自衛隊を派遣してきました。
テロ対策特別措置法
2001年9月11日のアメリカの同時多発テロ事件をきっかけに、日本は、テロ対策特別措置法を成立させて、アメリカ軍のテロリスト攻撃の後方支援をおこうため、インド洋北部など戦時の外国に自衛隊を派遣しました。
集団的自衛権
同盟国への攻撃を自国への攻撃とみなし、反撃できる権利を集団的自衛権といいます。国際的に、国連憲章などで認められている権利です。日本でも、2015年、集団的自衛権を認める安全保障関連法案が衆議院で可決されました。
自衛隊と日本の防衛の年表・年号
| 年号 | 内容 |
|---|---|
| 1950 | 朝鮮戦争勃発 |
| 警察予備隊創設 | |
| 1951 | 日米安全保障条約に調印 |
| 1952 | 保安隊に改組 |
| 1954 | 防衛庁設置、自衛隊発足 |
| 1960 | 新安保条約に調印 |
| 1972 | 沖縄返還 |
| 1991 | ペルシャ湾ヘ掃海艇派遣 |
| 1992 | 国際PKO協力法成立 |
| 1997 | 日米の防衛協力のための指針決定 |
| 2001 | テロ対策特別措置法成立 |
| 2007 | 防衛庁が防衛省に昇格 |
| 2015 | 安全保障関連法案が成立 |
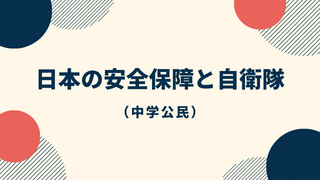
コメント