中学社会「公民の重要語句一覧」絶対暗記!です。
公民の重要語句一覧(高校入試対策社会)
間接民主制〔代議制〕
正当に選挙された国会における代表者を通じて、政治を行うしくみ (制度)のこと
立法機関
日本国憲法では、国会を、国権の最高機関であって唯一の立法機関であるとしている
特別国会〔特別会〕
日本国憲法では、衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に国会が召集され、内閣総理大臣が指名されることになっている国会
公職選挙法
国会議員の選挙区や定数などの選挙のしくみや方法について定めている法律。1994年には公職選挙法・政治資金規正法・政党助成法などを改正、成立させて政治改革をすすめた。
政令
内閣が、法律で決められたことを実施するために定めるきまり。内閣の仕事は、法律を実行する、条約を結ぶなどの外交、予算案や法律案をつくり国会に提出するなどの仕事がある。
違憲立法審査権(法令審査権)
裁判所が持っている、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限。下級裁判所にも権限があるが、最高裁判所が最終的な決定権をもつ。
三審制
わが国の裁判は、判決に不服な場合、上級の裁判所に控訴することができ、そこでの判決に不服な場合は、さらに上級の裁判所に上告することができるしくみ。
最高裁判所
わが国で、法律などが憲法に適合するかしないかの最終的な決定権をもち、「憲法の番人」と呼ばれある機関
高等裁判所
わが国における下級裁判所のうち、全国の8か所に設置されており、刑事裁判では、第二審が行われる裁判所。最高裁判所長官は、内閣が指名し天皇が任命する。その他の裁判官は、すべて内閣が任命する。
裁判員制度
地方裁判所における刑事裁判について、国民の中から選ばれた人が参加する制度が2009年から始まった制度。また、だれでも法律相談を受けることができる「法テラス」を通じ、 訴訟費用や弁護士費用の負担力のない人に対する法律扶助制度を利用できるようになった。
厚生労働省
社会福祉 社会保障および公衆衛生の向上をはかることを主な任務とする行政機関。
公正取引委員会
法律に基づいて、カルテルなど、私企業による独占を制限する仕事などにあたっている行政委員会。行政委員会は、政治的中立性や専門的知識を必要とする分野に設置され、一般の行政組織から独立した地位をもちます。
発券銀行
日本銀行は、日本で紙幣(日本銀行券) の発行を行 うただ一つの銀行である。このため、日本銀行は発券銀行と呼ばれる。日本銀行の役割にもとづく呼び名は、そのほかに、「銀行の銀行」、「政府の銀行」とがある。
累進課税 (制度)
所得税は、所得の再分配の考えにより、所得の多い人には税率を高くし、所得の少ない人には税率を低くしている課税制度
消費税
1989年に導入された、購入する商品やサービスにかけられる税金
製造物責任法 (PL法)
1995年、わが国では、製品の欠陥によって消費者が被害を受けた場合、その製造者は、過失の有無にかかわらず、被害者を救済しなければならないとする法律が施行された法律
公共料金
電車の運賃など、国会の議決や官公庁の承認を経て決まる料金。その種類として、国会や政府が決定するもの、政府が認可・上限認可するもの、政府に届け出るもの、地方公共団体が決定するものがある。
ベンチャー企業
近年、規模は小さくても、新しい産業分野を開拓したり、独自の技術を開発したりして、成長、発展する企業が注目されている企業
クーリング・オフ [クーリングオフ]
訪問販売などでいったん買う契約を結んでも、一定の期間内ならば消費者が契約を解除(解約) できる制度
ワーク・ライフ・バランス
仕事と生活の調和により、性別・年齢を問わず、誰もが働きやすいしくみをつくるという考え方
生存権
わが国の社会保障制度は、日本国憲法に定められ、また、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を国民に保障するための制度で、社会権に含まれるこの権利
国連教育科学文化機関 [UNESCO/ユネスコ]
国際連合の専門機関で、教育や文化などの国際協力の促進を主な目的とする機関
NGO
国際的な活動をしている民間の非政府組織の略称
ODA
わが国が発展途上国に提供している政府開発援助の略称
酸性雨
ヨーロッパや北アメリカの五大湖周辺では、森林が枯れる被害が広がっているがその原因とされる
温室効果ガス
地球環境問題の一つに地球温暖化がある。この原因となる二酸化炭素(CO2) などのガス。現在では、二酸化炭素やフロンガスが排出量を世界各国で削減しようと努力している。地球環境に優しい自動車やプラスチックなどの製品が返されている。
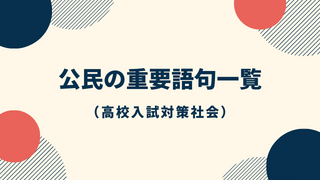
コメント