「漢字の成り立ち(象形・会意・指事・形成文字)」のまとめです。今回は、「象形文字」・「会意文字・「指事文字」・「形成文字」の学習です。漢字の成り立ちについては、辞書によって分類が異なる場合がありますが、入試では、そのような紛らわしい漢字ではでないので、問題集について問題の演習をしっかりやりこなせばいいでしょう。
漢字の成り立ちの定期テスト対策予想問題
まだ、勉強できていない人は、下にポイントを載せているので、そちらの勉強からしてください。
問1 次の(1)~(6)の漢字の成り立ちの説明として、適するものを後のア~カから選び記号で答えなさい。
(1)象形 (2)指事 (3)会意 (4)形声 (5)転注 (6)仮借
ア:すでにある象形文字や指事文字を組み合わせて、それぞれの意味を生かした新しい漢字を作ること。
イ:意味を表す要素と音を表す要素とを組み合わせて、新しい意味の漢字を作ること。
ウ:もともとの意味と関係のある別の意味に使い方を広げること。
エ:物の形をかたどって漢字を作ること。
オ:字のもとの意味とは無関係に、字の音だけを借りて他の意味を表すこと。
カ:形のない物事を、線や点で象徴化して表すこと。
問2 次の(1)~(8)の漢字の種類を後のア~カから一つずつ選び、記号で答えなさい。
(1)印度 (2)因 (3)板 (4)耳 (5)楽 (6)洗 (7)中 (8)炎
ア:象形文字
イ:指事文字
ウ:会意文字
エ:形声文字
オ:転注
カ:仮借
漢字の成り立ちの定期テスト対策予想問題解答
問1(1)エ (2)カ (3)ア (4)イ (5)ウ (6)オ
問2(1)カ (2)ウ (3)エ (4)ア (5)オ (6)エ (7)イ (8)ウ
漢字の成り立ちのポイント
「象形文字」・「会意文字・「指事文字」・「形成文字」のポイントや例について触れています。
象形文字
見た目のものや形や略画から作られた文字。
<例>
- 山
- 川
- 人
- 日
- 鳥
そのほかとして、手、父、心、爪、犬、木、牛、火、水などがあります。
会意文字
2つ以上の漢字を組み合わせて別の意味を表す文字
<例>
- 明は、「日」と「月」の組み合わせ。
件、安、列、各、印、争、因、后、旨、尽などがそれにあたります。
指事文字
形に押せない位置や数などを記号で表した文字。
<例>
- 上
- 下
- 一
- 二
- 三
その他として、共、至、朱、亦、亙、尖などがあります。
形声文字
意味を表す部分と音を表す部分を組み合わせた文字
<例>
- 銅…金と同の組み合わせ
草、芋、百、寺、存、扱、汗、旬、江、肌などがあります。
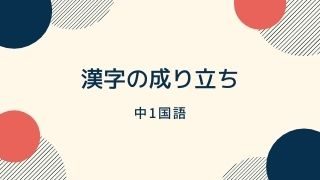
コメント