中3国語「おくのほそ道の定期テスト過去問分析問題」です。
- 俳句の形式…「五月雨をあつめて早し最上川」
- 切れ字…「閑さや岩にしみ入る蝉の声」
- 松尾芭蕉についてやその作品
の3点については、確実に押さえておきましょう。また、「おくのほそ道」の文章の展開は、学校の授業でのノートやプリントを何度も読み返し、インプットしておきましょう。
おくのほそ道の定期テスト過去問分析問題
次の文章を読んで後の問題に答えよ。
月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人なり。船の上に生涯を浮かべ、馬の口とらへて老いを迎ふる者は、日々旅にして旅を栖(すみか)とす。古人も多く旅に死せるあり。
予もいづれの年よりか、片雲の風に誘はれて、漂泊の思ひやまず、海浜にさすらへ、去年の秋、江上の破屋に蜘蛛の古巣をはらひて、やや年も暮れ、春立てる霞の空に、白河の関越えんと、そぞろ神の物につきて心を狂はせ、道祖神の招きにあひて取るもの手につかず、もも引の破れをつづり、笠の緒付けかへて、三里に灸すゆるより、松島の月まづ心にかかりて、住める方は人に譲り、杉風が別所に移るに、
草の戸も住み替はる代ぞ雛の家
表八句を庵の柱に掛け置く。
問一 次の歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直して、すべて平仮名で書け。
①くわかく ②かうしやう
問二 古文中にある次の漢字の読みを現代仮名遣いで、平仮名で書け。
①百代 ②去年
問三 「百代の過客」を口語訳せよ。
問四 「古人も多く旅に死せるあり」とあるが、この一文からどのような思いが感じられるか、次から1つ選べ。
ア 昔の人がしたように、多くの土地を旅行して見分を広めたい。
イ すばらしい詩人や歌人が旅の途中でなくなったのは、残念だ。
ウ 尊敬する古人と同様に旅をしながら、風雅の道をきわめたい。
エ 旅先で死んだりしないように、体力をつけておきたいものだ。
問五 「漂泊の思ひやまず」とは作者のどんな気持ちを述べているのか。次が1つ選べ。
ア 空を自由にただよいたいという気持ち。
イ 舟で漂白しているような不安な気持ち。
ウ あてもない旅をしたいという気持ち。
エ あちこち宿泊したいという気持ち。
問六 「江上の破屋」のことをこの後でどのように言い換えているか。俳句以外から二つ抜き出しなさい。
問七 作者が旅支度をしている部分を古文中で探し、その初めと終わりの三字を抜き出しなさい。
問八 作者がまず行きたいと思ったところはどこか。
問九 これまで何度も旅した経験がある作者が、今回の旅では特別な決意で身辺整理をしている。どんなことをしたのか。現代語で書け。
問十 次の( )に適当な言葉や人名を書け。ただし、アは漢字四字で書くこと。
おくのほそ道の定期テスト過去問分析問題の解答
問一 ①かかく ②こうしょう
問二 ①はくたい ②こぞ
問三 永遠の旅人
問四 ウ
問五 ウ
問六 住めるかた / 庵
問七 もも引 ~ すゆる
問八 松島
問九 住んでいる家を売った。(譲った。)
問十 ア 松尾芭蕉 イ 曾良 ウ おくのほそ道
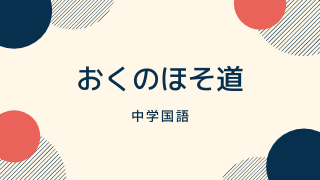
コメント