中学理科「顕微鏡の使い方のテスト対策問題」です。
【ポイント】中学理科「顕微鏡の使い方」
顕微鏡の練習問題
次の図を見て、次の問いに答えなさい。
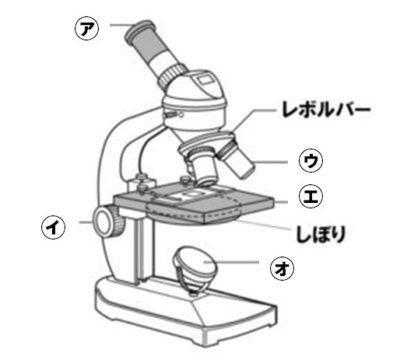
(1)図の顕微鏡の㋐~㋔の名前を答えなさい。
(2)顕微鏡で観察するときは、低倍率、高倍率のどちらからはじめるとよいか、答えなさい。
(3)ピントを合わせるときの操作について、下から正しいものを選び記号で答えなさい。
A ㋒のレンズとプレパラートをできるたけ近づけておいて、遠ざけながらピントを合わせる。
B ㋒のレンズとプレパラートをできるたけ遠ざけておいて、近づけながらピントを合わせる。
C ピントが合えば、どのような操作をしてもよい。
(4)接眼レンズを「15×」、対物レンズを「10」とした状態で観察すると、観察するものは何倍に拡大されたことになるか、答えなさい。
顕微鏡の練習問題の解答
(1)
㋐ 接眼レンズ
㋑ 調節ねじ
㋒ 対物レンズ
㋓ ステージ
㋔ 反射鏡
(2)低倍率
(3)A
(4)150倍
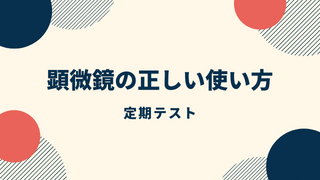
コメント