中学歴史「明治時代のまとめ」です。明治時代は、1868年から1912年までの期間で、日本が大きな変革を遂げ、新しい未来への一歩を踏み出した時代です。この時代は、国内では産業の発展や近代化が進み、国外では世界と交わることで新しい価値観を取り入れました。日本は欧米の文化や技術と触れ合い、洋服や鉄道、電信といった新しいものが次々と導入され、人々の生活が劇的に変わっていったのです。
| ▼明治時代を極めよう! |
|---|
| 中学歴史「明治時代の一問一答」 |
| 中学歴史「明治時代の対策問題」 |
明治時代のポイント
| 出来事 | 年号 | 内容 |
|---|---|---|
| ➊明治新政府 | 1868 | 五箇条の御誓文 |
| 1869 | 版籍奉還 | |
| 1871 | 廃藩置県 | |
| ➋明治維新 | 1872 | 学制の公布 |
| 1873 | 地租改正・徴兵令 | |
| ➌文明開花 | 1871 | 郵便制度 |
| 1872 | 鉄道開通 | |
| 1873 | 太陽暦を採用 | |
| ➍自由民権運動 | 1874 | 民選議員設立の建白 |
| 1880 | 国会期成同盟 | |
| 1881 | 国会開設の勅諭 | |
| ➎産業革命 | 1901 | 八幡製鉄所の操業 |
| 1894 | 領事裁判権の撤廃 | |
| 1911 | 関税自主権の完全回復 | |
| ➏大日本帝国憲法 | 1885 | 内閣制度創設 |
| 1889 | 大日本帝国憲法の発布 | |
| 1890 | 教育勅語の発布 | |
| ➐領土拡大 | 1894 | 日清戦争 |
| 1904 | 日露戦争 | |
| 1910 | 韓国併合 |
明治新政府
明治維新は、新政府の改革とそれに伴う社会の動き。政治の基本方針として、五箇条の御誓文を出した。江戸幕府を倒して新政府が樹立され、日本を近代国家にするために、さまざまな改革が実施された。この政治変革と、それにともなう社会の変化を明治維新とよんでいる。天皇を主権者とする政権として諸外国に認められた新政府は、1868年、政治の基本方針を示した五箇条の御誓文を出した。これは、天皇が公家や大名を率いて神にちかうという形をとった。このなかでは、世論の尊重、国民の一致協力、人心の一新 旧制度の改革、先進文明を取り入れることなどが述べられている。
中央集権国家の確立
新政府はまた、五箇条の御誓文を出した翌日に5枚の立て札を立て(五傍の掲示)、国民の守るべきこととして、殺人・放火・盗みの禁止、キリスト教の禁止などを示し、江戸幕府の政策を引きつぐことを示した。ついで、1868年7月に江戸を東京と改め、9月に年号を慶応から明治とし、翌年、首都を京都から東京に移して、新しい政治を進めていった。
- 五箇条の御誓文…新しい政治方針を示す。
- 版籍奉還…1869年大名に土地と人民を政府に返させた。
- 廃藩置県…1867年に藩を廃止して、府県を置き、中央から府知事・県令を派遣して治めさせた。中央集権国家の確立へ。
- 藩閥政治…倒幕に活躍した公家や薩摩・長州・土佐・肥前の4藩の出身者たちが政府の実権を握った。
- 身分制度の廃止…皇族以外全て平等であるとした。
- 解放令…差別されていた身分・職業を平民と同じとする布告。江戸時代の封建的な政治や身分の制度が廃止された。
岩倉使節団
明治新政府は、江戸幕府が結んだ不平等条約改正の交渉と欧米諸国の国情視察のため、1871年10月、岩倉具視を全権大使とし、大久保利通・木戸孝充・伊藤博文らを副使とする使節団を、アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国に派遣した。この岩倉使節団には団員約50名(政府有力者のほぼ半分が参加)のほか、津田梅子(のちに女子英学塾を設立)ら女子5名をふくむ約60名の留学生が加わっていた。条約改正の予備交渉は成功しなかったが、使節団一行は、もっぱら、欧米各国の政治制度や議会のようす、工場・学校・病院などの近代的施設を視察し、日本の国力を充実させ、近代化する必要性を痛感して帰国した(1873年9月)。
- 沖縄県の設置…1879年、軍事力を背景に、琉球の人々の反対を抑え、沖縄県を設置する。(琉球処分)
- 清との外交…1871年、対等な立場で日清修好条約を結ぶ。
朝鮮との外交
- 征韓論…武力で朝鮮に開国を迫ろうという主張。
- 日朝修好条規…1876年に結んだ朝鮮に不利な条約。
欧米との外交
- 樺太・千島交換条約…1875年ロシアと結ぶ。
- 小笠原諸島…1876年に日本の領有が決定。
- 千島列島・小笠原諸島・沖縄を領土として国境が確定する。
明治維新の三大改革
富国強兵を目指す。これは、新政府が、欧米の強国に対抗するために、介在を発展させて国力を向上させ、強力な軍隊を整備することを目指した方針。
学制
1872年に公布。6歳以上の男女に小学校の義務教育。国民すべてに小学校教育を受けさせることを目標。高等教育としては、1877年に東京大学が発足。また、教師を要請する官立の師範学校も作られた。
徴兵令
1873年から実施。満20歳以上の男子に兵役の義務。これによって、西洋式の常備軍が誕生し、近代的な軍隊制度が整った。しかし、この徴兵令は、士族の特権を奪うものであった。農民は、一家の労働力を奪うものとして、各地で徴兵令に反対する激しい一揆をおこした。
地租改正
1873年から実施。土地の所有者と地価を定めて、地券を発行し、地価の3%を地租として現金を納めさせた。政府の財政を安定させた。急激な改革に反対する人々の一揆が各地で起こった。その反面、地主は高率の小作料(小作地の使用料)を米で受け取り、その米を打って、地租を現金で納めたため、米の値上がりによって大きな利益を得た。
文明開花
欧米の文化が進んだ技術時取り入れられた。暦も欧米にあわせて、これまでの太陰暦をやめて大陽暦を採用し、明治5年(1872年)12月3日を明治6年(1873年) 1月1日とし、1日24時間制や七曜制も取り入れられた。これ以後、日曜日が休日とされるようになった。しかし、文明開化は大都市に限られ、農村では昔ながらの暦を使うなど、以前とあまり変わらない生活が続いた。
- 文明開化…欧米の文化が取り入れ生活が変化。
- 食事の変化…洋服・牛肉料理・洋館の建築など。
- 新しい暦…太陰暦から太陽暦を採用。
- 新しい思想…福澤諭吉が「学問のすすめ」を著す。
- 岩倉使節団…岩倉具視を全権大使として、木戸孝允・大久保利通らが欧米を視察。不平等条約の改正には失敗。
- 交通の整備…1872年新橋-横浜間に鉄道が開通。
- 北海道の開拓…開拓使が設置。屯田兵らが改革を進める。帰国した岩倉使節団の人々は日本の近代化を進めた。
殖産興業
近代的な産業を育成する政策。明治新政府が欧米諸国の進んだ経済制度、設備、機械、技術などを取り入れました。外国から機会を買い入れ、外国人技術者を招き、重要鉱山を直接経営するとともに、官営模範工場として群馬県の富岡製糸場などを設立。
自由民権運動
初めは土族が中心だった自由民権運動は、やがて、豪農 (大地主)や商工業者も参加する運動へと発展していった。1880年、民権派は愛国社を国会期成同盟と改称し、政府に 国会の開設を求める請願書を提出した。政府内でも、要職にあった大隈重信が速やかに国会を開設することを求めた。そうしたなか、1881年7月に開拓使官有物払い下げ事がおこり、民権派は政府攻撃をいっそう強めた。
国会開設の勅諭
政府は官有物の払い下げを中止して、民権派の大隈重信を政府から追放するとともに、国会開設の勅諭を出して、10年後(1890年)に国会を開くことを約束した。そこで、板垣退助らは1881年、フランスの民権思想の影響を受けた急進的な自由党を結成し、翌年、大隈重信らもイギリス流の議会政治と立憲君主制を理想とする立憲政進党を結成した自由民権運動の背景には、西洋での市民革命のなかで生まれた民主主義の考え方があって、植木枝盛などは、国民の自由と権利を守ることを人々によびかけた。また、民権運動の高まりのなかで、憲法や政治のしくみ を研究する学習会が全国各地で開かれ、民間でも憲法私案 (五日市憲法など)がさかんにつくられた。
- 西南戦争…1877年西郷隆盛を中心とした鹿児島の士族らがおこした反乱。徴兵制による政府軍に鎮圧された。
- 自由民権運動…議会政治の実現を目指す運動。
- 民選議員設立の建白書…1874年に板垣退助らが政府に提出した国会の開設を求める意見書。
- 国会期成同盟…1880年民権派の代表が大阪で結成。
- 国会開設の整備…政府が10年後に国会を開くこと約束。
政党の結成
- 自由党…1881年板垣退助を党首として結成。
- 立憲改進党…1882年大隈重信を党首として結成。
西南戦争後、政府に対する批判は武力による反乱から言論によるものへと変化した。
自由民権運動の終焉
西南戦争後に政府が財政を引きしめ、増税策をとったことから世の中は不景気となり、中・下層の農民が没落し、生活に苦しむ人々が増加した。自由党の急進派は貧農と結んで各地で蜂起し、福島事件や秩父事件(埼玉県)などがおこったが、政府は警察や軍隊の力で鎮圧した。この間、地方の党員を統制できなくなった自由党は解散し、豪農や商工業者らは民権運動の激化に不安を覚え、しだいにはなれていった。立憲改進党も、大隈重信の脱党で弱体化した。その後、政府が約束 した国会開設の時期が近づくと民権運動は再びもり上がりを見せたが、政府は保安条例などの法令で弾圧したり、政党の有力者を手なずけたりした。
秩父事件
1884年の、松方財政下では困民党に結集した農民たちが、秩父事件を起こした。秩父事件の前後には、加波山事件、飯田事件など、自由党員を主力とする一連の激化事件がおこっている。
日本の産業革命
日本では1880年代から20世紀初めにかけて産業革命がおこち、近代産業がめざましく発達しました。
- 軽工業…紡績業や製糸業で1880年代から日本の産業の中心となる。
- 八幡製鉄所…日清戦争で得た賠償金をもとに建設された官営の製鉄所。日本の重化学工業を支える。
- 財閥…金融や貿易など多くの業種に進出し、日本の経済に影響力を持った資本家。三菱・三井・住友など。
- 労働問題の発生…労働組合が形成されるようになり、労働条件の改善を求める労働争議は増加した。産業革命で軽工業が発達し、その後産業の中心は重化学工業へ移りました。
軽工業の発達
1880年代に、紡績業や製糸業などのせんい工業を中心に工場制機械工業が発達して、産業革命が始まった。国産の綿糸が大量に生産されるようになると、1897年以降、輸出が輸入を上回るようになった。日清戦争ごろからは、海外に市場が広がり、中国・朝鮮への綿糸や綿織物の輸出がのびて、紡績・織物工業が発達した。
重工業の形成
日清戦争後、ロシアとの対立が激しくなると、政府は軍事工業を中心に重工業の形成に努めた。日清戦争の賠償金の一部を使って、官営の八幡製鉄所を建設し、重工業形成の基礎となった。軍事工業や製鉄・造船・機械などの重工業製品がのびた。
このような中、資本主義が急速に発達し、政府の保護のもとに、小数の大資本家が多くの企業を系列下に入れて、資本経済を支配する財閥が形成されていった。
不平等条約の改正
明治政府が目指した不平等条約とは、1858年に江戸幕府が諸外国と結んだ修好通商条約で、日本が相手国に領事裁判権を認め、日本に関税自主権がないという不平等条約だった。
日本で罪を犯した外国人を、日本の法律では裁けない。裁くのは、外国の領事である。領事裁判権は、治外法権ともいう。■関税自主権がないとは?
日本に、輸入品にかける関税の率を自主的に決める権利がない。近代国家の間では、たがいに関税自主権をもつのが常識である。
ノルマントン号事件
1886年のノルマントン号事件をきっかけに、日米修好通商条約の不平等な内容改正し、欧米諸国と対等な地位を得ようとした。1886年、イギリス船ノルマントン号が紀州(和歌山県)沖で沈没し、イギリス人船員は全員ボートで脱出したが、日本人乗客は全員死亡という事件がおこっ た。これを裁いたイギリス領事は、はじめ過失責任なしとして船長を無罪にした。
- 欧化政策…外務卿(のちに外務大臣)の井上馨は、日本が欧米同様の文明国であることを示し、改正交渉を有利に進めようとして、鹿鳴館で舞踏会を開くなどした極端な政策
- 関税自主権の回復…1878年に一部の国が合意したが実現せず、1894年に一部回復。1911年に小村寿太郎が交渉し、完全に回復する。
- 領事裁判権の撤廃…1894年外務大臣の陸奥宗光が領事裁判権を撤廃した条約をイギリスと結び実現。
日本は、憲法の制定と条約改正により欧米諸国と対等の地位となり帝国主義へ傾いていきます。
大日本帝国憲法の発布
正負は、1882年より、伊藤博文をヨーロッパに派遣して各国の憲法を調査させた。伊藤博文らは、天皇制を確立するため、君主制が強いドイツ(プロセイン)の憲法を手本にして、秘密のうちに憲法草案を作成。
枢密院の審議を経て、1889年2月11日、天皇が国民にあたえるという形(欽定憲法)で、大日本帝国憲法として発布。この憲法では、主権は天皇にあり、天皇は国の統治権、陸海軍の統帥権など、多くの絶対的な権限をもつとされた。
- 内閣制度…1885年創設。初代内閣総理大臣は伊藤博文。
- 大日本帝国憲法…1889年発布。君主権の強いドイツ(プロイセン)の憲法を手本とする。
- 教育勅語…1890年発布。忠君愛国の道徳が示された。
帝国議会
国民は、「天皇の臣民」とされ、制限付きながら、さまざまな自由が与えられ、国政に参加する道が開かれた。
- 貴族院と衆議院を置く二院制を採用。
- 第1回衆議院議員選挙…選挙権は直接国税15円以上納める満25歳以上の男子に与えられた。憲法のもとで国民が政治参加する道が開かれた。
日清戦争
1876年に日朝修好条規を結んだのち、日本の商人らが朝鮮半島にわたって、米や大豆を安く買い入れ、日本の綿製品を大量に売ったりしたため、朝鮮国内では食料が不足するなど、経済が混乱した。そのうえ、重税でなどで人々は、苦しい生活を送っていました。そんな状況の中で起こるのが、日清戦争です。
日清戦争は、朝鮮半島をめぐる日本と清が戦争を開始。1890年甲午農民戦争をきっかけに始まった朝鮮をめぐる日本と清の戦争。結果は、日本が勝利し、下関条約を結ぶ。
甲午農民戦争
東学(民間信仰をもとにした朝鮮の宗教)を信仰する人々を中心とする農民が朝鮮戦闘南部一体で蜂起。政治改革や外国人の排除を目指しました。
三国干渉
ロシア・ドイツ・フランスが日本が下関条約で獲得した遼東半島を清に返還するように勧告し、日本は要求に従った。清が衰え、日本や欧米諸国に分割された。
八幡製鉄所
賠償金で日本の重化学工業張の発展の基礎を気づいた官営の八幡製鉄所も、建設された。
下関条約
日清戦争の講和条約。台湾を統治した日本は、台湾総督府を設置して。植民地化を進める。
清は、
- 遼東半島・台湾・澎湖諸島を日本にゆずる。
- 賠償金として、2億両(約3億円)を日本にゆずる。
- 不平等な内容の通商条約を日本と結ぶ。
日露戦争
欧米列強の侵略を受けてきた清では、外国人排斥の運動が高まってきた。このころ、中国の秘密結社である義和団という宗教団体が「扶清滅洋(清を助けて西洋人を追いはらう)」と唱えて民衆の支持を得て、外国人排斥の運動を進めていた。
列強の中国分裂に反発して蜂起した義和団を日本を中心とする連合軍が鎮圧した事件。
ロシアの南下・日本の大陸進出という2つの政策が満州・韓国をむぐって衝突し、対立がより深まっていった。戦争の危機が迫る中、日本では、新聞・雑誌などは主戦論を展開し、三国干渉の影響もあって、主戦論が圧倒的になり、開戦。1904年に始まりその後、日本は物資が不足し、ロシアの国内は混乱して、両国とも戦争の継続が難しくなり、1905年に締結。日露戦争で苦戦を重ねながら勝利をおさめたカタチ。
1902年ロシアに対抗する日本と中国の利権拡大を狙うイギリスが結んだ同盟。
ポーツマス条約
1905年アメリカの仲介で結ばれた日露戦争の講和条約。中国進出をはかろうとするアメリカ合衆国は、日本・ロシアのどちらかの一方の決定的な勝利を望まなかった。そこで、ル-ズベルト大統領が講和を仲介した。
・韓国における日本の優越権を認める。
・遼東半島の租借権を日本に認める。
・南満州鉄道の権利を日本に譲る。
・樺太の南半分を日本の領土とすること。
日比谷焼き討ち事件
日露戦争の犠牲の大きさに対し賠償金が得られないことから国民がおこした暴動。日本は列強としての地位を固め、大陸の進出を狙う。
韓国併合

ポーツマス条約によって韓国における優越権を得た日本は、1905年に韓国を保護国とし、漢城(現在のソウル)に韓国総督府おいて韓国の外交権をうばいました。韓国総督府の初代韓国統監は、伊藤博文でしたが、満州のハルビンを訪問した際、韓国の義兵運動家の安重根に射殺される。
- 韓国併合では、1910年日本が朝鮮総督府を置き、武力を背景に韓国を植民地化した。学校では日本人に同化させる教育が行われた。
辛亥革命
中国では、列強諸国による侵略に抵抗する動きが強まり、腐敗した清を倒して、漢民族の独立を勝ち取り、近代国家をつくろとする革命運動がさかんになっていた。こうした民衆の動きに応じて、中国南部の長江中流域の武昌(現在の武漢)で軍隊が反乱を起こしたのが、辛亥革命。
- 孫文…中国の革命家。三民主義を唱え中国の革命の中心人物となる。
- 辛亥革命…1911年全国広まった近代国家の建設を目指す革命運動。多くの省から清から独立を宣言。
- 中華民国…1912年孫文が臨時大総統になり建国。アジアで最初の共和国。首都は南京。袁世凱が孫文とともに清の皇帝を退位させ、清が滅亡する。辛亥革命で清が滅亡し、中華民国が成立する。
明治文化
欧米の影響を受け、それまでとは違った文化が現れる。
- 文化…近代文学と芸術が発達する。美術では日本の伝統的な美術の価値が見直された。
- 教育の普及…全国に小学校が設置され、就学率が高まる。欧米の文化を取り入れ、日本の新しい文化が生まれる。
<近代文化の医学・自然科学者のおもな業績>
| 分野 | 人物 | 業績 |
|---|---|---|
| 医学 | 北里柴三郎 | 破傷風の血清療法 |
| 志賀潔 | 赤痢菌の発見 | |
| 野口英世 | 黄熱病の研究 | |
| 化学 | 高奉譲吉 | ジアスターゼの創製 |
| 鈴木梅太郎 | ビタミンB1の創製 | |
| 物理学 | 大森房吉 | 地震計の研究 |
| 木村栄 | 緯度変化の研究 | |
| 長岡半太郎 | 原子模型の研究 |
<近代文化の文学・美術のおもな作品>
| 分野 | 人物 | おもな作品 |
|---|---|---|
| 文学 | 島崎藤村 | 若菜集、破壊 |
| 与謝野晶子 | みだれ髪 | |
| 樋口一葉 | たけくらべ | |
| 石川啄木 | 一握の砂 | |
| 森鴎外 | 舞姫、雁 | |
| 夏目漱石 | 坊っちゃん | |
| 美術 | 黒田清輝 | 読書 |
| 横山大観 | 無我 | |
| 高村光雲 | 老猿 |
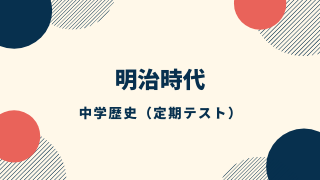
コメント