中2理科の「ジュールの法則」についてまとめています。ジュールの法則は、「電熱線に発生する熱量は、電流・電圧・時間との積に比例する。」ということが、ポイントです。ジュールの法則について詳しくみていきましょう。それでは、中2理科の「ジュールの法則」のまとめです。
ジュールの法則
電熱器に電流が流れると、熱が発生して温度が上がります。抵抗に発生する熱量は、電流と電圧の積に比例しています。導体(電気を通す物質)に電流が流れと熱を発生する。この熱をジュール熱といいます。
熱量計、可変抵抗器、電熱線、電流計、電圧計などを接続し、電熱線に発生する熱量を水温の上昇から求めます。電流、電圧、抵抗を変えて調べると、つぎの関係のあることがわかります。
抵抗Rの物体に流れる電流をI (A)、両端の電圧をE[V] とすると、t秒間に発生する熱量Q[J]は Q=E×I×t → Q=電力✕時間(t)
この関係をジュールの法則といいます。
練習問題を解く 「電熱線による水の温度変化の定期テスト過去問分析問題」
直列のときのジュール熱
抵抗を直列につないだときに、それぞれの抵抗に発生するジュール熱は、抵抗が大きいほど大きく、抵抗の大きさに比例します。
並列のときのジュール熱
抵抗を並列につないだときに、それぞれの抵抗に発生するジュール熱は、抵抗が小さいほど大きく、抵抗の大きさに反比例します。
並列につないだ抵抗の1つの抵抗値を変えるとその抵抗で発生する熱量は変わりますが、他の抵抗で発生する熱量にはかわりありません。しかし、直列につないだ場合には、1つの抵抗値が変わると、その回路を流れる電流の大きさがが変わるため、他の抵抗に発生する熱量も変わってきます。 このため、家庭で使う電気器具は、並列にして電源につなぎ、他の電気器具の影響を受けないようにしています。
ジュール熱の利用
ジュール熱を利用した代表的な装置は、電熱器と白熱電球です。 そのほか、ジュール熱を利用したものに、電気 炉などがあります。
電熱器
電流による発熱を利用して熱を得るための装置。種類には、電気コンロ・電気ストーブ・電気アイロン・トースター・電気がま・電気ごたつ・電気毛布・電気ポット・ 電気はんだごてなどがあります。
電熱器は、発熱体と発熱体のショート(短絡) を防ぐ絶縁体とからできています。電熱線に用いるものには、融点が高いこと、高温でも酸化しにくいこと、抵抗が大きいこと、線や板に加工しやすいことなどの条件が必要です。ふつうは、ニクロム線などが用いられています。
練習問題を解く 「消費電力と発熱量の定期テスト過去問分析問題」
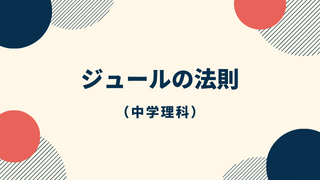
コメント