中学歴史「江戸時代に関する一問一答」です。
江戸時代に関する一問一答
次の問いに答えなさい。
- 1600年に、徳川家康が石田三成らを倒した戦いを何というか。
- 無断で城を改築することなどを禁じた大名統制令を何というか。
- 大名に、1年おきに領地と江戸を往復させた制度を何というか。
- 江戸幕府が天皇や公家の行動を制限するために定めたものは何か。
- 徳川家康がすすめた東南アジアとの貿易を何というか。
- 国交を回復したのちの朝鮮から、日本にやってきた使節を何というか。
- 江戸時代、農業生産力の向上に役立った、土地を深く耕す道具は何か。
- 手工業の原料として取引された、麻やわたなどの作物を何というか。
- 江戸、大阪とならんで三都とよばれた都市はどこか。
- 大阪に多く設置された、幕府や諸藩が米などを貯蔵する蔵を何というか。
- 都市での営業を独占した、大商人たちによる同業者組合を何というか。
- 元禄文化が栄えたころの5代将軍は誰か。
- 俳諧を大勢させ、「奥の細道」を著した人物は誰か。
- 徳川吉宗の政策で、参勤交代の期間を短くするかわりに、米を幕府におさめさせた制度を何というか。
- 大衆の意見を広く聞くために設けられた投書箱を何というか。
- 農民が費用や農具を買うようになって、農村に広まった経済を何というか。
- 大商人などが、工場で人をやとって行う手工業の形式を何というか。(カタカナ9文字)
- 大商人に対して都市の民衆がおこした暴動を何というか。
- 田沼意次が、税を取って特権を与えた商工業者の団体を何というか。
- 松平定信が厳しい倹約策を行った改革を何というか。
- 「古事記伝」などにみられる、日本の古典を研究する学問を何というか。
- オランダ語を通じてヨーロッパの技術を研究する学問を何というか。
- 19世紀の初め、江戸の庶民が担い手となった文化を何というか。
- 江戸時代後半に活躍した浮世絵師で、美人画で優れた作品を残した人物は誰か。
- 外国船の接近が増えたために、1825年に出された法令は何ですか。
- 1837年に、大阪で奉行所の対応に不満をもち、反乱をおこした人物は誰か。
- 天保の改革を行った老中は誰か。
- 天保の改革で実施された、庶民のえいたくを禁止する決まりを何というか。
- 1858年に幕府がアメリカを結んだ、日本に不利な条約を何というか。
- 日本には輸入品の関税率を決める権利がなかったが、この権利を何というか。
- 天皇を尊び、外国の勢力を排除しようとする運動を何というか。
- 安政の大獄への反発から、水戸藩の浪士たちが大老の井伊直弼を暗殺した事件を何というか。
- 1867年に、15代将軍徳川慶喜が天皇に政権を返上したことを何というか。
- 1868年に始まった、旧幕府軍と新政府軍との戦争を何というか。
- 長州藩と薩摩藩は、1866年に同盟を結び、倒幕へと動き出した同盟を何というか。
江戸時代に関する一問一答の解答
- 関ヶ原の戦い
- 武家諸法度
- 参勤交代
- 禁中並公家諸法度
- 朱印船貿易
- 朝鮮通信使
- 備中ぐわ
- 商品作物
- 京都
- 蔵屋敷
- 株仲間
- 徳川綱吉
- 松尾芭蕉
- 上げ米の制
- 目安箱
- 貨幣経済
- マニュファクチャア
- 打ちこわし
- 株仲間
- 寛政の改革
- 国学
- 蘭学
- 化政文化
- 喜多川歌麿
- 異国船打払令
- 大塩平八郎
- 水野忠邦
- 倹約令
- 日米修好通商条約
- 関税自主権
- 尊王攘夷運動
- 桜田門外の変
- 大政奉還
- 戊辰戦争
- 薩長同盟
復習しておこう!
江戸時代(1603年~1868年)は、徳川家康が江戸幕府を開いたことで始まりました。260年以上の平和と安定が続き、参勤交代制度や武家諸法度で大名を統制しました。農業が発展し、町人文化が栄え、浮世絵や歌舞伎が隆盛しました。鎖国政策により、海外との交流は制限されましたが、長崎の出島を通じてオランダや中国と貿易を行いました。後期には、天保の改革などの幕政改革が行われましたが、経済困難や外国船の来航が増え、最終的に明治維新によって幕府は崩壊しました。
江戸時代(1603年~1868年)は、徳川家康が江戸幕府を開いたことで始まりました。260年以上の平和と安定が続き、参勤交代制度や武家諸法度で大名を統制しました。農業が発展し、町人文化が栄え、浮世絵や歌舞伎が隆盛しました。鎖国政策により、海外との交流は制限されましたが、長崎の出島を通じてオランダや中国と貿易を行いました。後期には、天保の改革などの幕政改革が行われましたが、経済困難や外国船の来航が増え、最終的に明治維新によって幕府は崩壊しました。
【対策問題】中学歴史「江戸時代のテスト対策問題」
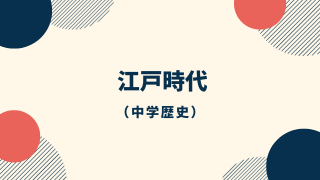
コメント