中2理科「湿度の求め方のポイント」です。
この単元では、飽和水蒸気量と気温のグラフから、露点、湿度を求めたり、気温・湿度・グラフから露点など求めさせたり、グラフに関する出題が多いです。また、雲のでき方を実験で問う問題、湿度の計算問題もよく出ます。そのあたりをみていきましょう。
湿度の計算(求め方)
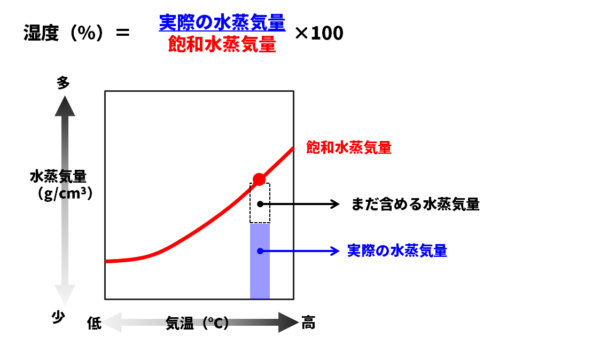
- 湿度(%)=(空気中に含まれる水蒸気量(g/m3)/そのときの気温の飽和水蒸気量(g/m3))×100
湿度は、空気の湿り具合。単位はパーセント(%)。
<練習問題>
1m3中に10.4gの水蒸気を含む20℃の空気の湿度は何パーセントか。20℃の空気の飽和水蒸気量は17.3g/m3である。
<解説・解答>
先ほどの公式に与えられた数値をそのままあてはめると、
(10.4÷17.3)×100=60.1
露点
露点とは飽和水蒸気に達したときの温度のことです。
- 飽和…限度いっぱいまで水蒸気を含んだ状態。
- 飽和水蒸気量…空気1m3に含むことができる水蒸気の最大量。単位はg/m3で、気温が高いほど大きい。
- 露点…空気中の水蒸気の一部が凝結し始める温度。気体から液体になるときで、空気中の水蒸気量が大きいほど多い。
乾湿計と湿度
乾球の示度と乾球と湿球の示度の差を湿度表にあてはめる。湿度が低いほど乾球と湿球の示度の差が大きい。
湿度の性質・変化
気温が高いほど湿度低く、気温が低いほど湿度高い。
- 晴れの日…気温が高くなると湿度は低くなり、気温が低くなると温度は高くなる。気温と湿度は反対の変化。
- 雨の日…普通、湿度は高いのであまり変化しない。
乾湿計の利用の解き方(手順)
- 乾球の示度にあたる気温を確認する。(気温=乾球の示度)
- 乾球の示度と湿球の示度の差を確認する。
- 乾球の示度とその差がクロスしたところが湿度となる。
乾湿計のポイント
- 常に乾球の示度は湿球の示度(温度)以上である。
- 乾球の示度と乾球と湿球の示度の差を湿度表にあてはめる。湿度が低いほど乾球と湿球の示度の差が大きい。
【対策問題】中2理科「湿度を求めるテスト対策問題」
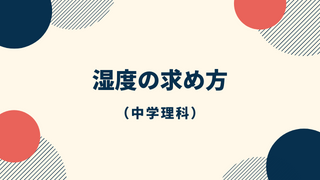
コメント