中学理科「セキツイ動物に関するテスト対策問題」です。
セキツイ動物の対策問題
【問】次の表は、現在生息しているセキツイ動物を5つのなかまに分けたものである。これについて、あとの問いに答えなさい。
| 項目 | ホニュウ類 | 鳥類 | ハチュウ類 | 両生類 | 魚類 |
|---|---|---|---|---|---|
| うまれ方 | B | 卵生(陸上に産卵) | 卵生(水中に産卵) | ||
| 体温 | つねに一定 | A | |||
| 呼吸 | 肺呼吸 | C | えら呼吸 | ||
| 体表 | 毛 | 羽毛 | うろこ・こうら | 皮ふ裸出 | うろこ |
(1) セキツイ動物が共通してもっているつくりは何か。
(2) 図のA、Bにあてはまる言葉をそれぞれ書きなさい。
(3) 次の文は、表のCについてまとめたものである。1、2にあてはまる呼吸器官をそれぞれ書きなさい。
両生類は、卵からかえった直後は、( 1 )で呼吸しているが、成体になってからは皮膚と( 2 )で呼吸する。
(4) ハチュウ類とホニュウ類にふくまれる動物を、次のアからエからそれぞれ選びなさい。
ア:トカゲ イ:イモリ ウ:クジラ エ:ハト
セキツイ動物の対策問題の解答
(1) 背骨
背骨をもつ動物のなかまをセキツイ動物、背骨をもたない動物のなかまを無セキツイ動物という。
(2) A…変温 B…胎生
(3) 1えら 2肺
両生類は、水中で生活する子のときはえらで呼吸をし、水辺で生活する成体のときはと皮膚で呼吸をする。
(4)ハチュウ類:ア / ホニュウ類:ウ
イモリは両生類、ハトは鳥類である。
復習しておこう!
セキツイ動物は、脊椎(背骨)を持つ動物群で、魚類、両生類、ハ虫類、鳥類、哺乳類の5つに分類されます。魚類は水中で生活し、エラで呼吸します。両生類は幼生期は水中で、成体になると陸上でも生活でき、皮膚と肺で呼吸します。ハ虫類は乾燥した環境に適応し、肺で呼吸し、鱗(うろこ)に覆われています。鳥類は翼を持ち、多くは飛ぶ能力があり、肺で呼吸し、恒温動物です。哺乳類は体毛を持ち、肺で呼吸し、母乳で子を育て、恒温動物です。各分類ごとの特徴を理解することが重要です。
セキツイ動物は、脊椎(背骨)を持つ動物群で、魚類、両生類、ハ虫類、鳥類、哺乳類の5つに分類されます。魚類は水中で生活し、エラで呼吸します。両生類は幼生期は水中で、成体になると陸上でも生活でき、皮膚と肺で呼吸します。ハ虫類は乾燥した環境に適応し、肺で呼吸し、鱗(うろこ)に覆われています。鳥類は翼を持ち、多くは飛ぶ能力があり、肺で呼吸し、恒温動物です。哺乳類は体毛を持ち、肺で呼吸し、母乳で子を育て、恒温動物です。各分類ごとの特徴を理解することが重要です。
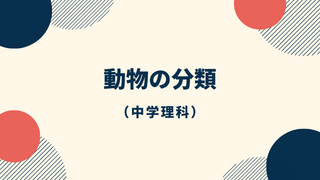
コメント