中1理科「音に関する一問一答」
音の現象に関する一問一答
次の問いに答えよ。( )には適語入れよ。
(1)音は、音の大きさ、音の高さ、音色の3つの要素で表すことができる、これを何というか。
(2)音の高さは、( )が多いほど、音は高い。
(3)弦を強くはじくと、( )音になる。
(4)音と低くするには、弦を( )くする・弦を太くする・弦を弱く張るのいずれかである。
(5)振動して音を発生しているものを何というか。
(6)音の伝わり方は、( )が振動して伝わる
(7)音は、気体、液体、固体では、どの状態が早く伝わるか。
(8)自ら音を出している物体を何というか。
(9)振動が次々と伝わる現象を何というか。
(10)音が伝わらないのは、どんな状態にあるときか。
(11)音は1秒間にどれくらいの距離を進むか。
(12)同じ高さの音を出す音さを2つ並べて、一方を鳴らすと、もう一方も鳴り始める。この現象を何をいうか。
(13)音源の振幅が大きいほど、音はどうなるか。
(14)振動数とは、何の回数か。
(15)音源の振動数が多いほど、音はどうなるか。
(16)振動数の単位は、カタカナで何か。
(17)振動数の単位は、アルファベットでどう書くか。
(18)均質な鋼をU字型にまげて、中央に柄をつけてものを何というか。
(19)音の大小や高低を、波形で表す装置を何というか。
(20)音源が近づくときは音が高くなり、音源が遠ざかるときは音が低くなる現象を何というか。
音の現象に関する一問一答の解答
(1)音の三要素
(2)振動する回数(振動数)
(3)大きい
(4)長
(5)音源
(6)空気
(7)気体
(8)音源
(9)波
(10)真空中
(11)340m
(12)共鳴
(13)音が大きくなる
(14)1秒間に振動する回数
(15)音が高くなる
(16)ヘルツ
(17)Hz
(18)音さ
(19)オシロスコープ
(20)ドップラー効果
高い音は、振動数が多く、波長が短い。低い音は、振動数は少なく、波長が長い。
大きい音は、振幅が大きく、小さい音は、振幅が小さい。

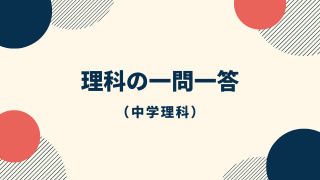
コメント